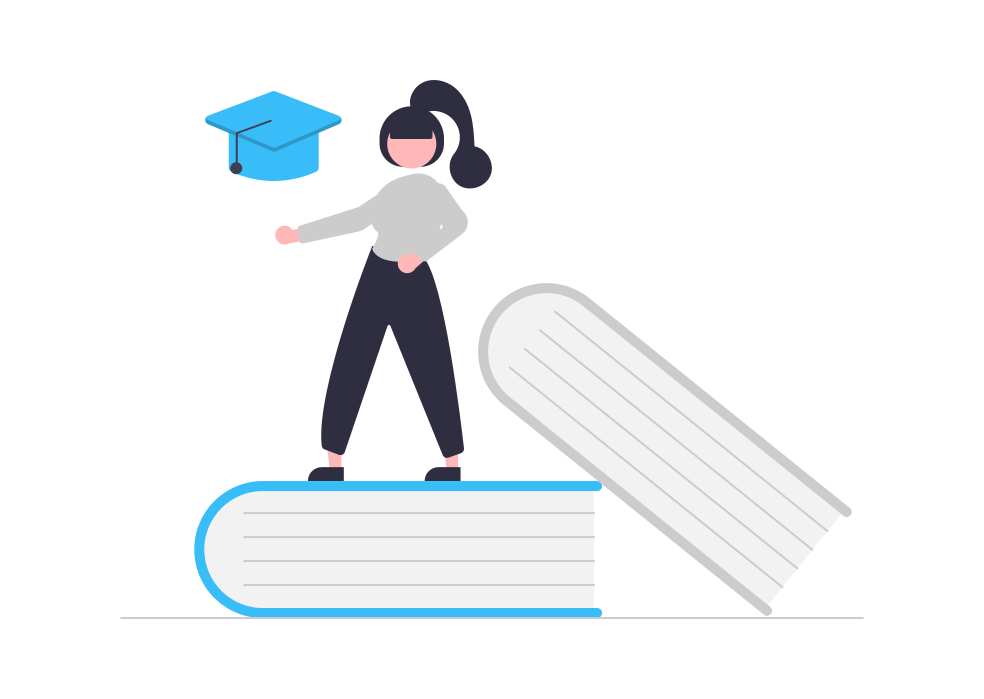インフラエンジニアを目指す方や、スキルアップのために資格取得を考えている方は多いのではないでしょうか?
でも、「たくさん資格があって、どれから取ればいいんだろう?」「資格を取っても実務で活かせるの?」と悩んでいませんか?
実は私も、インフラエンジニアとしてのキャリアを始めた頃、同じ悩みを抱えていました。
この記事では、インフラエンジニアがステップアップしていくためにおすすめの資格取得順序と実務での活用例をまとめました。
これから資格取得を目指す方の「最初の一歩」をサポートできれば嬉しいです!

- 現役のフルスタックエンジニアとして活躍中
- 開発チームリーダーとして複数プロジェクトをリード
- 副業プログラミングスクール講師として数百名以上を指導してきた教育のプロ
- プログラミングスクールのカリキュラム執筆経験あり
この記事を読むとわかること
- インフラエンジニア向け資格の種類と最適な取得順序
- それぞれの資格が実務でどう活かせるのか
- 資格取得で気をつけるべきポイント
- 現場で役立つ技術スタックとの関連性
- 資格取得後のキャリアステップの考え方
まず押さえておきたい基礎資格
「インフラエンジニア」と聞くと、難しいサーバー管理やネットワーク構築をイメージするかもしれませんね。
でも、最初に取り組むべき資格は意外とシンプルな基礎領域なんです。
ネットワークの基礎を学ぶなら「CCNA」
ネットワークの入門資格として、CCNA(Cisco Certified Network Associate)は非常に人気があります。
CCNAでは、IPアドレスの仕組みやルーティング、スイッチングといった基本的な概念を学べます。
実務では、こんな場面で役立ちます。
- オフィスネットワークのトラブルシューティング
- クライアントVPNの設定と管理
- ルーターやスイッチの基本設定
Linuxサーバーの基本を学ぶなら「LPIC-1」
サーバー運用では、Linuxを使うケースが非常に多いです。
そのため、LPIC-1やLinuC レベル1などのLinux系資格も早めに取得しておくと安心です。
LPIC-1では以下のような基本的なLinux知識を身につけられます。
- 基本的なLinuxコマンド操作
- ファイルシステムの管理
- ユーザー管理やアクセス権限の設定
- シェルスクリプトの基礎
実務では、サーバーの運用監視やトラブル発生時の対応で頻繁に使います。
例えば、「なぜかサービスが落ちた!」というときに、ログファイルを確認したり、ディスク容量を調べたりといった基本操作が必須になるんですね。
最初は抽象的な内容も多いですが、実際の業務で「サーバーが遅い時はどこを見ればいいのか」「ログはどう確認するのか」など、具体的な視点を養う基礎になるので、焦らず学んでいきましょう!
ネットワークとサーバーの次に学ぶべき資格
基礎ができたら、次はどんな資格に進むべきでしょうか?
ネットワークとLinuxの基本が身についたなら、クラウド関連の資格がおすすめです。
クラウドの基礎を学ぶならAWS認定資格
クラウドサービスの中でも特に利用者の多いAWSには、体系的な認定資格制度があります。
初めてクラウドを学ぶなら、以下の順序でステップアップするといいでしょう。
- AWS Certified Cloud Practitioner(クラウドの基礎知識)
- AWS Certified Solutions Architect – Associate(クラウド設計の基礎)
実務ではこんな場面で活かせます。
| 資格名 | 実務での活用例 |
| Cloud Practitioner | ・AWSの基本サービスの理解 ・クラウドコスト管理の基礎 ・クラウドセキュリティの基本概念 |
| Solutions Architect | ・EC2、S3、RDSなどの主要サービスの設計 ・可用性の高いアーキテクチャの構築 ・セキュリティグループやIAMの設定 |
最近ではほとんどのシステムがクラウドを使うようになってきました。
オンプレミスから移行するケースも多いので、「ネットワーク」「Linux」「クラウド」の3つの知識があると、幅広いプロジェクトで活躍できますよ。
多くのエンジニアは、ネットワークとLinuxを学んでから、AWSなどのクラウドに進む傾向があります。これは、クラウド環境でもネットワークやサーバーの基礎知識が必要になるからです。
効率化と自動化のための次のステップ
基礎とクラウドの知識を身につけたら、次は運用の効率化や自動化を視野に入れましょう。
この段階で学ぶと良い技術は以下のようなものです。
コンテナ技術:Docker・Kubernetes
DockerやKubernetesといったコンテナ技術は、アプリケーションのデプロイや環境の再現性を高めるのに役立ちます。
特に形式的な資格はありませんが、「Docker Certified Associate」や「Certified Kubernetes Administrator」などの認定試験があります。
これらの技術は実務でこんな場面で活躍します。
- 開発環境と本番環境の差異をなくす
- マイクロサービスアーキテクチャの構築
- スケーラブルなシステム運用の実現
IaC(Infrastructure as Code):Terraform
Terraformは、インフラ環境をコードで管理する「IaC(Infrastructure as Code)」ツールです。
「HashiCorp Certified: Terraform Associate」という認定資格もあります。
例えば、以下のようなシンプルなコードでAWSの仮想マシンを管理できます。
provider "aws" {
region = "ap-northeast-1"
}
resource "aws_instance" "example_server" {
ami = "ami-12345678"
instance_type = "t2.micro"
tags = {
Name = "example-server"
}
}実務では、こんな場面で活用できます。
- 複数環境(開発・ステージング・本番)の一括管理
- インフラ構成の履歴管理とバージョン管理
- 環境構築の再現性向上と自動化
自動化系のツールは、ネットワークやLinux、クラウドの基礎がないと理解しにくいことがあります。まずは基礎をしっかり固めてから、効率化ツールに進むとスムーズですよ!
セキュリティ資格のベストタイミング
セキュリティは重要な分野ですが、いつ勉強するのがベストなのでしょうか?
基本的には、ネットワークやサーバーの基礎知識がある程度身についた段階で学ぶのがおすすめです。
全くの初心者がいきなり高度なセキュリティ資格に挑戦すると、暗号化やアクセス制御などの概念で躓くことがあります。
セキュリティ関連でおすすめの資格は以下のとおりです。
| レベル | おすすめ資格 | 特徴 |
| 入門〜初級 | 情報セキュリティマネジメント試験 | 基礎的なセキュリティ知識を学べる 実務未経験者でも取得しやすい |
| 中級 | CompTIA Security+ | 実践的なセキュリティスキルを習得 国際的に認知された資格 |
| 上級 | 情報処理安全確保支援士 (登録セキスペ) | 国家資格としての価値が高い 高度なセキュリティ対策を学べる |
実務では、こんな場面でセキュリティの知識が活かせます。
- 脆弱性スキャン結果の適切な対応
- ファイアウォールやIDSの設定
- インシデント発生時の適切な対応手順
- セキュリティポリシーの策定と実装
資格取得で意識したい3つのポイント
資格を取得する際には、以下のポイントを意識するとより効果的です。
1. 実務で使う技術から優先的に学ぶ
例えば、オンプレミスサーバーを管理する環境なら、まずはLinuxやネットワーク関連の資格を優先するといいでしょう。
クラウド移行が進んでいる環境なら、AWS認定資格などの方が直接役立つかもしれません。
自分の職場や希望する職場でよく使われている技術を把握し、そこから学んでいくのが効率的です。
2. 資格学習と実務を連動させる
資格学習で得た知識をすぐに実務に活かせる環境があるなら、理解度も格段に上がります。
既にインフラエンジニアとして働いている方じゃないと難しいかもしれませんが、たとえば以下のようなアプローチを試してみるといいでしょう。
- AWSの資格を取得したら、社内でのサーバー移行プロジェクトに参加してみる
- Linuxの資格を取得したら、社内サーバーの運用改善を提案してみる
- ネットワーク資格を取得したら、オフィスネットワークの設計を手伝ってみる
このように、学んだ知識を実践の場で使うことで、より深い理解につながります。
3. 幅よりも深さを意識する
多くの資格を持っていても、実際に運用する知識が浅いと、実務では評価されにくいです。
まずは基礎をしっかり身につけ、その上で関連領域を広げていくアプローチが効果的です。
例えば、Linuxの資格を取ったら、実際に手元でサーバーを立てて運用してみる。ネットワークの資格を取ったら、自宅で仮想環境を作ってルーティングの設定を試してみるなど、実際に手を動かす機会を作ることが大切です。
実務経験がない場合でも、自宅の環境やクラウドの無料枠を活用して、小さなテスト環境を作り、実践的なスキルを身につけることができます。これにより、面接時にも具体的な経験をアピールできます。
インフラエンジニア向け資格の系統イメージ
インフラエンジニアの資格取得パスを図で表すと、以下のようなイメージになります。
| ステップ | 分野 | おすすめ資格 |
| 基礎レベル (0〜1年目) | ネットワーク基礎 Linuxサーバー基礎 | ・CCNA ・LPIC-1/LinuC レベル1 ・基本情報技術者試験 |
| 初級〜中級 (1〜2年目) | クラウド基礎 セキュリティ基礎 | ・AWS Certified Cloud Practitioner ・AWS Solutions Architect Associate ・情報セキュリティマネジメント試験 |
| 中級〜上級 (2〜3年目) | 自動化・効率化 クラウド応用 | ・Terraform Associate ・Docker/Kubernetes認定 ・AWS Professional/Specialty資格 |
| 上級 (3年目以降) | 高度なセキュリティ アーキテクチャ設計 | ・情報処理安全確保支援士 ・CISSP ・応用情報技術者試験 |
これはあくまで一般的なイメージです。実際には、自分の興味や職場環境に合わせてカスタマイズするといいでしょう。
まとめ
インフラエンジニアとして資格を取得していく流れをまとめてみましょう。
まずはネットワーク(CCNA)やLinux(LPIC-1)などの基礎からスタートし、次にクラウド(AWS資格)の知識を身につけていくのが効率的です。
ある程度基礎ができたら、コンテナ技術(Docker/Kubernetes)やIaC(Terraform)などの自動化・効率化ツールを学び、並行してセキュリティ関連の知識も身につけていくといいでしょう。
資格取得の際は、以下のポイントを忘れないでください。
- 実務で使う技術から優先的に学ぶ
- 資格学習と実務を連動させる
- 幅よりも深さを意識する
資格取得はあくまでもスタート地点です。実際の現場で知識を活かし、実践経験を積んでいくことで、真のインフラエンジニアとして成長していけるでしょう。
みなさんが資格取得を通じてスキルアップし、キャリアを広げていけることを願っています!
資格はあくまでも入り口です。本当に大切なのは、実務でどれだけ応用できるかということ。知識と経験をバランスよく積み重ねて、インフラエンジニアとしての成長を楽しんでいきましょう!
インフラエンジニアとしてさらにスキルアップするには?
近年、SRE というポジションが人気を集めています。
簡単に言うと、インフラやクラウドのスキルを使ってシステムや開発プロセスの改善を行うようなポジションです。
Webサービスが増えている昨今、海外でも注目を集めており、年収も上昇傾向にあります。
スキルアップ&年収アップを目指している方は、必要スキルだけでも理解しておくと今後の参考になるかと思います!